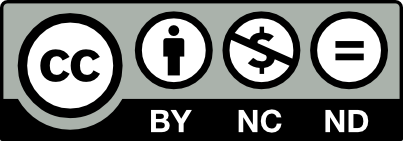
引用文を除く文章の著作権は椿耕太郎にあり、クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に公開する。
原文・書き下し文の前の数字と現代語訳の前の数字が異なるため違うこともあるが、原文・書き下し文に対応する現代語訳をすぐ下に載せている。引用文は緑の点線で囲っている。
2023年11月7日 椿 耕太郎
十五之二一
子曰、「君子矜而不爭、群而不黨。」
子曰く、君子は矜にして爭はず、群して黨せず。
二一(四〇〇)
先師がいわれた。――
「君子はほこりをもって高く己を持するが、争いはしない。また社会的にひろく人と交るが、党派的にはならない。」
十五之十六
子曰、「群居終日、言不及義、好行小慧、難矣哉。」
子曰く、群居終日、言義に及ばず、好んで小慧を行ふ、難いかな。
一六(三九五)
先師がいわれた。
「朝から晩まで多勢集っていながら、話が道義にふれず、小ざかしいことをやって得意になっているようでは、見込なしだ。」
十四之三三
子曰、「不逆詐、不億不信、抑亦先覺者、是賢乎。」
子曰く、逆め詐とせず、億りて信あらずとせず、抑〻亦先覺者は、是れ賢なるか。
三三(三六五)
先師がいわれた。――
「だまされはしないかと邪推したり、疑われはしないかと取越苦労をしたりしないで、虚心に相手に接しながら、しかも相手の本心がわかるようであれば、賢者といえようか。」
十五之二二
子曰、「君子不以言舉人、不以人廢言。」
子曰く、君子は言を以て人を擧げず、人を以て言を廢せず。
二二(四〇一)
先師がいわれた。――
「君子は、言うことがりっぱだからといって人を挙用しないし、人がだめだからといって、その人の善い言葉をすてはしない。」
十二之二四
子貢問「友」。子曰、「忠吿而善道之、不可則止、毋自辱焉。」
子貢友を問ふ。子曰く、忠吿して善く之を道き、不可ざれば則ち止む、自ら辱めらるること無し。
二三(三〇一)
子貢が交友の道をたずねた。先師はこたえられた。――
「真心こめて忠告しあい、善導しあうのが友人の道だ。しかし、忠告善導が駄目だったら、やめるがいい。無理をして自分を辱しめるような破目になってはならない。」
十二之二五
曾子曰、「君子以文會友、以友輔仁。」
曾子曰く、君子は文を以て友を會し、友を以て仁を輔く。
二四(三〇二)
曾先生がいわれた。――
「君子は、教養を中心にして友人と相会し、友情によって仁をたすけあうものである。」
十五之三九
子曰、「道不同、不相爲謀。」
子曰く、道同じからざれば、相爲に謀らず。
三九(四一八)
先師がいわれた。――
「志す道がちがっている人とは、お互いに助けあわぬがいい。」
十之十五
朋友死、無所歸、曰、「於我殯。」朋友之饋、雖車馬、非祭肉、不拜。
朋友死して、歸する所なきときは、曰く、我に於て殯せよと。朋友の饋は、車馬と雖も、祭肉に非ざれば拜せず。
一五(二五〇)
先生は、友人が死んで遺骸の引取り手がないと、「私のうちで仮入棺をさせよう」といわれる。
先生は、友人からの贈物だと、それが車馬のような高価なものでも、拝して受けられることはない。ただ拝して受けられるのは、祭の供物にした肉の場合だけである。
十六之四
孔子曰、「益者三友、損者三友、友直、友諒、友多聞、益矣。友便辟、友善柔、友便佞、損矣。」
孔子曰く、益者三友、損者三友。直を友とし、諒を友とし、多聞を友とするは益なり。便辟を友とし、善柔を友とし、便佞を友とするは損なり。
四(四二四)
先師がいわれた。――
「益友に三種、損友に三種ある。直言する人、信実な人、多識な人、これが益友である。形式家、盲従者、口上手、これが損友である。」